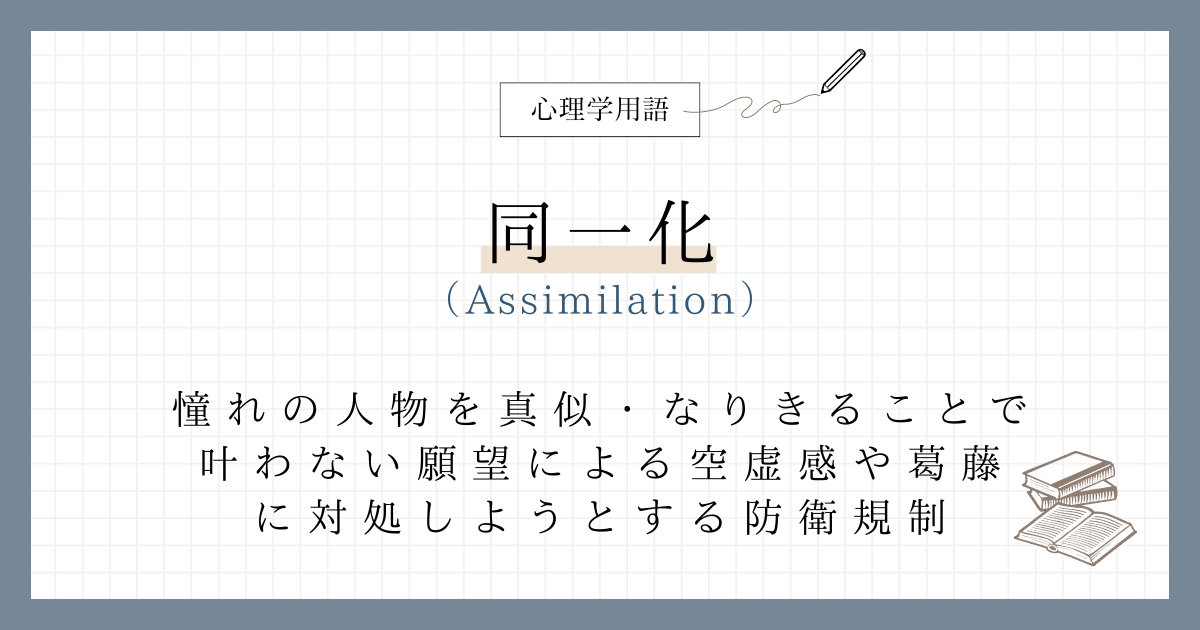同一化とは
同一化とは、自分にとって重要な人物の真似をすることを通して、叶わない願望による空虚感・葛藤に対処する防衛機制です。
- 親や兄弟の真似をする
- 憧れの芸能人の服装や髪型を真似する
といった経験がある方は多いのではないでしょうか。実は、こうした同一化(別名:同一視)は、ヒトが「発達」していく上で重要な役割を果たします。
補足:防衛機制とは
防衛機制とは、認めがたい自分自身の感情や欲求、不安や葛藤などといった「耐えがたい感情」を感じずにするための無意識の”対処法”のことです。例をいくつか見てみましょう。
- 反動形成
本心とは反対の行動を取る(例:好きな女の子に意地悪をする) - 知性化
知識を用いて客観的に処理しようとする(例:フラれた理由を冷静に分析する) - 合理化
自分に都合の良いように事実を歪曲して「自分は正しい」と納得する(例:フラれたときに「あんな性格が悪い人とは付き合わなくて正解だ」と思い込む)
精神分析の創始者であるオーストリアの精神科医「ジークムント・フロイト」が提唱し、後に娘の「アンナ・フロイト」によって、さらに体系化されました。
同一化とは
防衛機制の「取り入れ」との違い
同じく防衛機制の「取り入れ」という防衛機制が似ているので違いを解説していきます。
- 取り入れ(introjection)
理想対象の「一部分」を取り込むこと - 同一化(identification)
理想対象の「全て」を取り込むこと
この「取り入れ」は「同一化」の前段階であるとされています。
同一化の提唱者はフロイト
防衛機制を最初に提唱したフロイトは、3~6歳の男の子の超自我の形成や男性としての性役割のためにも父親への同一化の重要性を述べています。
フロイトは、男児自身が父親より劣っていること(心理学ではエディプス・コンプレックスとも)に対処するために意識的・無意識的に努力するものだというのです。
つまり、同一化は子どもが発達していく原動力になると同時に同性の親へのライバルとしての敵対意識に対する防衛機制として働くという訳です。
参考:超自我
フロイトは人間の心は超自我、自我、イド(エス)の3つの働きで成り立っているとしました。超自我は「道徳心」や「良心」。それに対してイドは「本能的で快楽主義的」な部分を指します。自我は超自我とイドのバランスを現実を鑑みながら調整する役割を持っています。
参考:エディプス・コンプレックス
ギリシャ神話のエディプス王に由来するもの。フロイトによれば3~6歳の男児は母親への愛着を持つと同時に父親への敵意を抱くようになるとされます。
(フロイトの提唱する理論上は)母親の愛着は性的な関心を含んだものであるとされ、男児はそれ故に父親にその母親への愛着と父親への敵意が去勢という形で罰せられるのではと恐れるのです。
罰されず、そして、母親の愛情を得つづけるためにも男児は母親の愛する父親への同一化をすると考えていました。その結果、超自我や自らの性役割を獲得するとしました。
同一化の日常例
同一化の日常例#1
自分がかっこいいと思うモデルの髪型や恰好を真似する
髪型や恰好を真似することによって、「自分なんて可愛くない」という葛藤や「自分に自信が持てない…」といった不安を軽減させることが出来ます。
どこか一部でも真似をするだけでまるでその人になったかのような、自分とは全く別の人物になれた気持ちになれることもありますよね。
髪型や恰好を取り入れるのは比較的かんたんにできる方法ですし、同一化の例としても皆さんが一番分かりやすいのではないかと思います。
同一化の日常例#2
自分のあこがれの人の習慣や考えを真似る
髪型や恰好だけでなく、習慣や考え方といった目に見えない部分もあります。憧れの人を真似ることで「自分はできない…」という不安や葛藤を少しでも和らげようとします。例えば、仕事のデキる先輩の仕事の仕方を真似るだけでも、少しは自分も仕事がデキる人になれた気がしませんか?
仕事上のあこがれの人のモットーを自分もモットーにしていたり、同じようなことを自分も習慣化させてみたりと見た目を真似るよりもこちらの方がその人自身の在り方に大きく影響するかもしれませんね。
最後に
同一化は真似ることで自身の不安や葛藤を取り除くだけでなく、自尊心の向上や自分の在り方を変化するきっかけにもつながります。
「真似る」ということに「自主性がない」等のネガティブなイメージを持たれる方もいるかとは思いますが、子どもが親やきょうだいの真似をしながら何かを学んでいくようにそれは人が成長していくための大切な要因なのです。
大人になってもそれは同じでいきなり何のお手本もなしにできる人はごく少数でしょう。同一化することでもっと自分を好きになれたり、新しい自分になれたりするのかもしれません。最初はただの真似でも徐々にあなたらしさも加わっていくことでしょう。
防衛機制である「同一化」。はじめは自分自身の不安や葛藤からの無意識的な行動かもしれませんが、それがあなたの成長のきっかけにもつながるかもしれませんね。